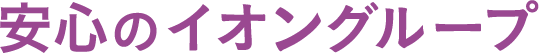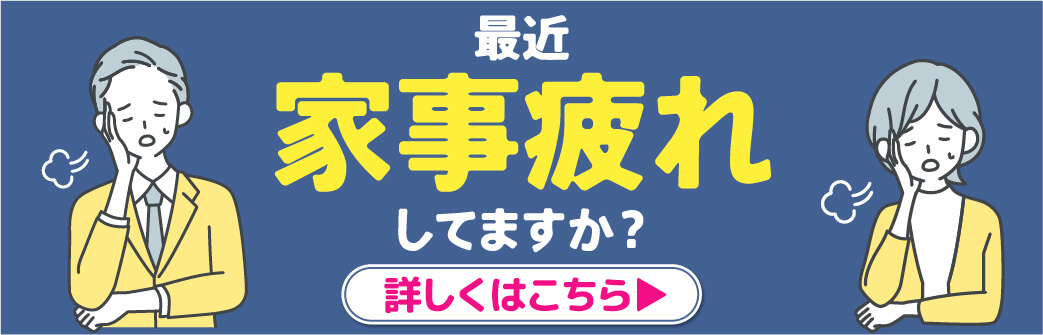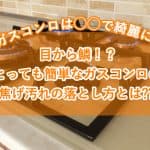本記事では、日々の家事に疲れ、家事のこなし方に悩んでいる方に向けて、家事で疲れてしまうときの「よくあるパターン」と、「自分を労わるための方法」について実例を交えて紹介しています。
目次
1.「家事疲れ」のよくあるパターン5つ
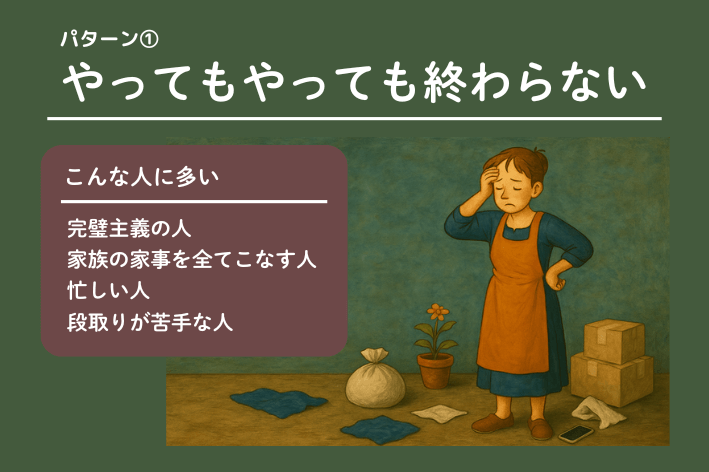



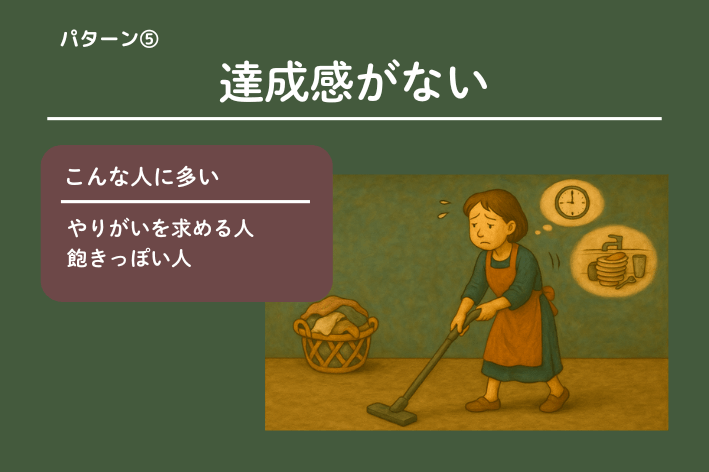
「家事疲れ」は日々こなすべき家事を負担に感じ、ストレスを感じたり、心身ともにしんどいと感じたりする状態のことです。
ここでは「家事疲れ」をどんなときに感じやすいか、よくあるパターンを5つ紹介します。
【パターン1】家事をやってもやっても終わらない

- 完璧主義の人
- 家族の家事をこなす人
- 忙しい人
- 段取りが苦手な人
家事をやってもやっても際限なくやることが見つかってしまうと、げんなりしてしまい「家事疲れ」を感じやすくなります。
家事は炊事洗濯掃除だけにとどまりません。また、手間をかければいくらでもでき、やろうと思えばいくらでも出てくるものです。
いくらこなしても「終わり」が見えないと、ストレスを感じやすい状態になります。
また、家事をこなす時間が限られている場合も、「家事が十分にできない」「やってもやっても次の日へ持ち越さなければならない」といった感情に苛まれることがあります。
こちらの記事も併せてご覧ください。
【パターン2】家事と仕事の両立がうまくいってない

- フルタイムで働いている人
- 一人暮らしの人
- 体力に自信がない人
仕事をしている人によくあるのが、家事と仕事の両立がうまくいかずに家事が疎かになっているパターンです。
仕事から疲れて帰ってきてから、さらに疲れる家事をこなすためには精神力が必要なこともあります。
また、タイムオーバーで今日やるべき家事を明日に持ち越すと、さらに疲労感を感じるといった悪循環に陥りがちです。
こちらの記事も併せてご覧ください。
【パターン3】家事負担が自分に集中している

- 2人以上で暮らしている人
- 夫婦共働き
- 専業主婦
- パートナーがルーズだと感じている人
夫婦やパートナーと一緒に暮らす人の一方に家事負担が偏っているときに「家事がしんどい」と感じるパターンです。
最近は共働き世帯も増え、家事の分担が課題となることも増えています。
事前に話し合って家事を分担しても、家事には「名もなき家事」があることからどちらか片方に負担感が増すことがあります。
また、専業主婦の場合、ワンオペで家事をこなすと代わりがいない状態となり「家事疲れ」へつながるケースも見られます。
こちらの記事も併せてご覧ください。
【パターン4】感謝されない

- 家事を完璧にこなせてしまう人
- 協力を得るのが苦手な人
日々こなす家事は意外と重労働にもかかわらず、労いの言葉一つかけられない状態でモチベーションを失うパターンです。
家事は生活に必要不可欠であることから「やって当たり前」と捉えられてしまうこともしばしばです。家族の生活を支えるための家事なのに、それを当然とされてしまうと「何のためにやっているのだろう」と疲労感を覚える方も多いでしょう。
また、一人暮らしでも自分のために頑張っている家事を「やれて当たり前」と捉えると、徐々に「家事疲れ」を感じやすくなります。
【パターン5】達成感がない

- やりがいを求める人
- 飽きっぽい人
家事はルーティン化していることも多く、達成感を感じにくいことが特徴です。
目標を設定しづらいため、達成感を感じづらいことが「家事疲れ」を感じやすくなる一因となります。
こちらの記事も併せてご覧ください。
2.家事疲れしている「自分を労わる」ための方法 5つ
毎日家事に追われて、疲れを感じている「自分を労わる」ための方法を5つまとめました。

2-1.完璧を求めない
家事は完璧を求めすぎると、自分を追い詰める結果になりかねません。
家事の特徴として、「やろうと思えばいくらでもやることがある」ということが挙げられます。
「もっと綺麗にできる」「もっと自分でできる」という感覚で家事をこなそうとすると「家事疲れ」を引き起こしやすくなるでしょう。
おすすめは「メリハリ家事」です。
昨日はがんばったから今日は手抜きできるところは手を抜くといった「メリハリ」のある家事で、ストレスを溜めないようにします。
2-2.全部やり切ろうとしない
全部やり切ろうとすると、家事をするのが億劫になったり、終わらなかった罪悪感を抱いたりしがちです。
そこで、家事に優先順位をつけて無理せずできる量に減らす=「全部やり切ろうとしないこと」が大切です。
そうすれば、一つひとつこなすごとに小さな達成感を感じることができ、疲れも軽減されます。
家事を「どうしても今日やらなければならないこと」「何日までにやるべきこと」「急ぎではないがやるべきこと」に分けて、優先順位が高い順からこなしていきましょう。
ひとつ終わったら、自分へのご褒美タイムを作るのもお勧めです。
2-3.家族で家事分担を見直す
家事には「名もなき家事」と言われるものがあります。
こうした家事も含めて、不公平な分担としないためには家事をジャンルごとに大まかに分担することがおすすめです。
それぞれの得意不得意も鑑みながら話し合うとよいでしょう。
家事分担の詳細はこちらの記事で解説しています。
2-4.家事の効率化を図る
2-5.家事をアウトソーシングする
「家事のアウトソーシング」とは、家事代行やハウスクリーニングを依頼することです。
苦手な家事をプロに依頼することで、心のゆとりが生まれるでしょう。
3.「家事疲れ」のよくある事例
「家事疲れ」の状態に陥ってしまった方の事例を3つ紹介します。
また、それぞれの事例での家事疲れを労わるための方法も解説しています。
事例①
東京都にお住まいの会社員Oさん
生活スタイル
会社員をしているOさんは、都内に一人暮らし。4月にプロジェクトリーダーを任され、仕事で充実した毎日を過ごしています。
家事疲れの経緯
プロジェクトリーダーを任された頃から業務量が格段に増え、平日は残業をこなすことが多くなりました。
それまでは帰宅後にこなせていた家事も時間を捻出するのが難しくなり、使わなくなった冬物が片付かずに日々荒れていく室内を見て「疲れ」を感じながら最低限の家事をこなすだけになりました。
もともと完璧主義者なところがあったOさんは、こなせていた家事ができなくなったことにストレスを溜め、「家事疲れ」の状態に陥ったと考えられます。
家事疲れを労わるための方法
一番のストレスの元となっていた「片付かない冬物衣類」を、「保管サービス付きの宅配クリーニング」に依頼しました。
部屋が片付いて気分が一新できたうえに、毎日のちょっとした片付けで綺麗な状態が続くようになり、帰宅後の家事疲れを感じにくくなりました。
また、衣類を来季まで保管してもらえる業者に依頼したことから、スペース不足の悩みからも解放されました。
事例②
埼玉県にお住まいの会社員Sさん
生活スタイル
会社員のSさんは、現在育休中。夫は3カ月の育休の後職場復帰しており、現在平日昼間はワンオペで育児に家事に追われています。
家事疲れの経緯
フルタイムで働いていたSさんは、産休育休に入ったことから家事分担の比重を増やしても大丈夫だろうと、もともとは夫が担当していた家事も自分がこなせると宣言。子どもが生まれ夫の育休期間が終わると、育児に家事にと負担が激増してしまいました。
自分から言い出した手前、夫に相談することもできず、一人密かに「家事疲れ」の状態に陥ったと考えられます。
家事疲れを労わるための方法
Sさんは負担が増えた家事の現状を夫に相談。家事分担を見直して、無理のない生活に戻すことができました。
加えて、Sさんは家事で一番苦手な「掃除」をプロに任せることにしました。
赤ちゃんのいる環境で使うエアコンのカビ汚れが気になっていたこともあり「エアコンクリーニング」と、子どもがいると入念に掃除できない「浴室・お風呂クリーニング」を依頼。
赤ちゃんの使う環境を綺麗に整えることができ、お風呂も簡単な手入れで綺麗が持続できるため、家事疲れから解放されました。
事例③
青森県にお住まいの専業主婦Kさん
生活スタイル
Kさんは長年、専業主婦として家族を支えてきました。
子どもが成長するとパートも始め、生活面でも金銭面でも家族を支えるように。昨年長女が就職し社会人となりましたが、現在も一緒に住んでいます。
家事疲れの経緯
昨年長女が就職したのをきっかけに、当たり前のように整った家で気ままに過ごす姿を見て、違和感を覚えるように。
いままで当然のようにやってきた家事が楽になるどころか、負担が増えたように感じるようになりました。
誰からも感謝されることもなく、すべての家事を担ってきたことに気づいてモチベーションを一気に失い、「家事疲れ」の状態になってしまいました。
家事疲れを労わるための方法
Kさんは家族会議を開催。
家事の負担を家族で分散して、いままで何もしてこなかった家族にも徐々に家事を担ってもらうことにしました。
また、ワンオペ家事ではなかなか手が回らなかった「レンジフードクリーニング」を業者に依頼。日頃の懸念も綺麗さっぱりクリーニングすることに成功しました。